和太鼓は日本の伝統的な打楽器。
そして、和太鼓を演奏する際にはいろいろな和楽器が使われています。
その中でも特に多く目にするのが、篠笛(しのぶえ)、摺鉦(すりがね)、チャッパになります。
今回は、その篠笛、摺鉦、チャッパにスポットを当てて紹介していきたいと思います。
初心者さん、必見です!!
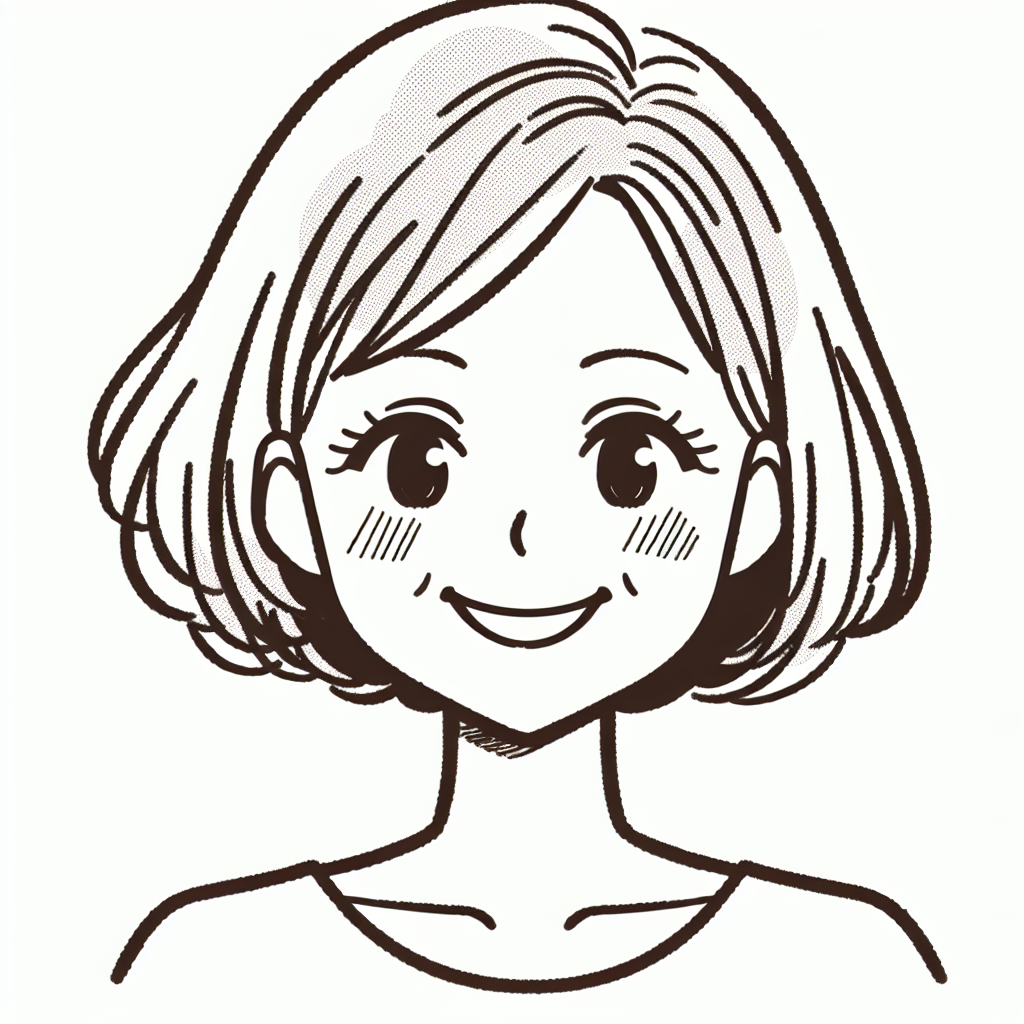
篠笛や鉦などが使えるようになったら、
演者としてステップアップした気持ちになれますよ♪
和楽器・篠笛の紹介
篠笛は、和太鼓と共に和楽器の中でも重要な役割を果たしています。
篠笛は和太鼓ととても相性がいいといわれています。
和太鼓のリズムに合わせて、篠笛の美しい音色が奏でられることで、和太鼓の音楽に深みを加えてくれ、一層魅力を増してくれるといえます。

篠笛の特徴と種類
【篠笛の特徴】
- 篠笛は、竹製の横笛の一種
現在はプラスティック製のものもあります
- 音域は低音から高音まで広く、透明で清らかな音色
- 祭りや舞台芸能、雅楽などで和太鼓と共に演奏されることが多く、和太鼓の音色とのマッチング度が高い
- 調子によって運指や楽譜が異なるわけではなく、同じ運指で演奏できる移調楽器
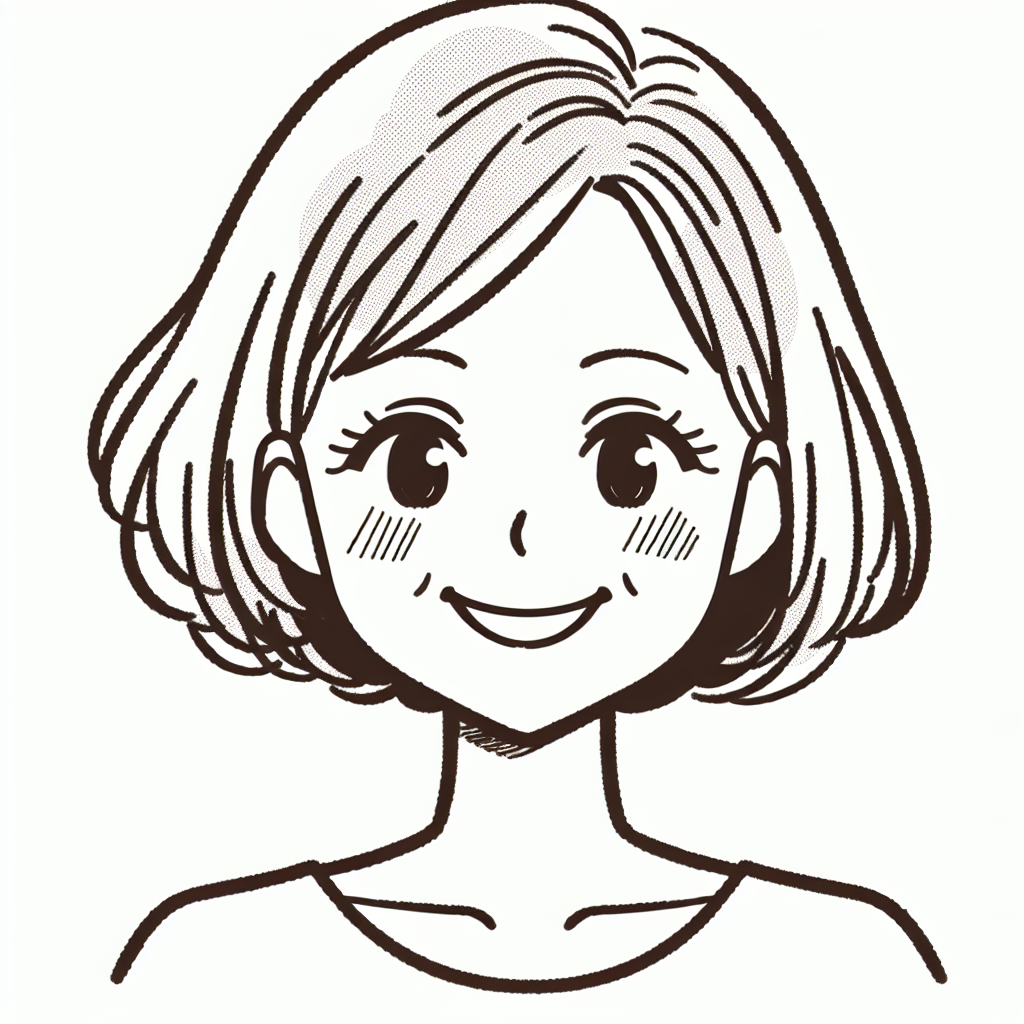
澄んだ音色に心打たれるのですが、
力強さもあるんです!
【篠笛の種類】
=調子による分類=
篠笛は半音ずつ調子が違う笛が12本あります。
ドレミ調に使われる数字譜は、指使いを表しており、
同じ数字譜でも調子が違うと、同じ音程にはならないのです。
調子とは音の高さのことになります。
篠笛の頭の部分に漢数字が書いてあり、低い調子の一本調子から、最も高いとされる十二本調子まであります。
低音のものほど長く、反対に高音のものほど短くなっています。
そのため、女性やお子様など手の小さめの方が一人で吹かれる場合は、高音の調子のものを選ぶと指も合いやすく、奏でやすいですね。
よく使われるのは、次の3種類だと思います。

=用途による分類=
< 囃子用篠笛(古典調)>
指穴の大きさと間隔が、ほぼほぼ均等に作られています。
地域や作者によって音程が異なるため、地域の笛方に確認して同じブランドの笛を選ぶほうがよいでしょう。
全国で統一した規格はないようです。
同じ六本調子の笛といいながらも、地域や作者によって半音程度の音程の相違があったりします。
<唄用篠笛 ドレミ調 >
長唄や民謡を奏でるために、指穴の大きさや間隔を変えて調律した篠笛が、唄用篠笛です。
全音、半音の相対配列はどの調子の笛も共通になります。
篠笛は、いろいろ他にも特徴・違いがあるのですが、初心者には少し難しくなるので、今後また詳しく紹介していきますね。
篠笛の演奏の方法
横笛のように吹く楽器ですが、独特の指使いと呼吸法が必要になります。
息の調整と指の動きを同時に行って演奏するので、やはり練習が必要になってきますね。
まずは、音を出せるようになるのが大切で、音が出ると楽しくなるので、上達も早くなりますね。
焦らず、取り組んでいきましょう。
篠笛の演奏には、以下のようなポイントがあります。
1. 息の出し方
- 唇は自然な形から、軽くほほえむ感じにして唇の真ん中に小さな穴を開ける
- 細くまっすぐ息が出るように意識する
- 顔の中心と吹き口の中心を合わせる
2. 指の使い方
- 指全体ではなく、必要な筋肉にだけ力を入れる「脱力」が大切
- 指の力を抜いて、軽やかに指を動かす
3. 音程の取り方
- 息の強弱を調整して、高音域と低音域をコントロールする
- 指の位置を微調整して、正確な音程を出す

篠笛の選ぶときの注意点
篠笛を選ぶときの注意点として、下記のことを考えるとよいと思います。
初心者は、安価なプラスティック製のものを購入してもよいと思います。
それで、息の出し方、指の使い方、音程のとり方をしっかり練習しましょう。
音をまともに出すまでが大変で、少し出せるようになるとうれしくなってがんばる気持ちがわいてきます。
プラスティック製のものだからといって、音色が悪いわけではありません。
私自身も竹製の篠笛とプラスティック製の篠笛を持っていますが、竹製の方が必ずしもいつもよい音が出るということではないのです。
もちろん、演者の技量によるところも多いと思いますが、その日の湿度や自身の息の入れ方でも違いがありそうです。
篠笛は奥深い楽器ですが、基本的な吹き方を習得すれば、誰でも美しい音色を出すことができます。
日々の練習と、篠笛との対話?を大切にしながら、篠笛の魅力を探っていきたいですね。
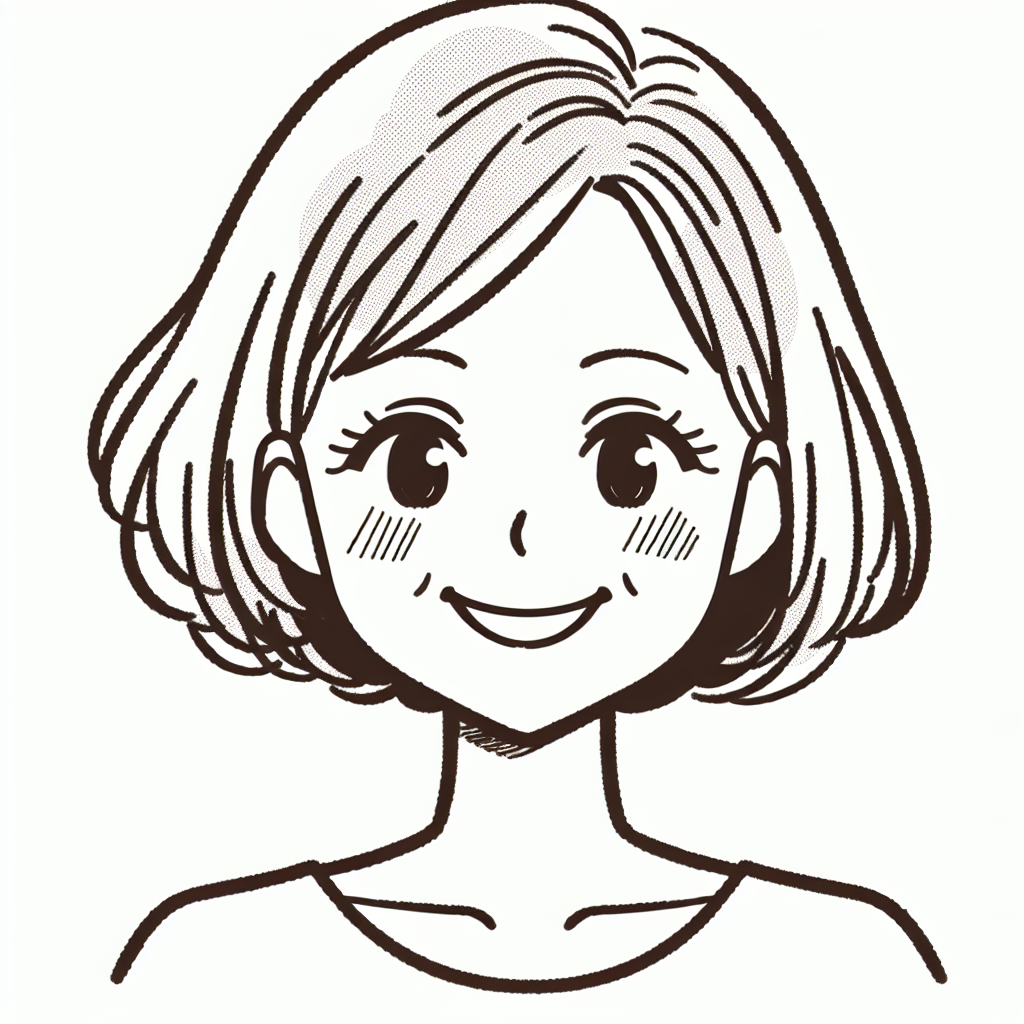
私自身は、長胴太鼓や締太鼓の基本打ちができるようになってから、
プラスティック製篠笛を購入し、練習を始めました。
和楽器・摺鉦の紹介
摺鉦(すりがね)は日本の伝統的な打楽器で、金属製です。
当り鉦(あたりがね)やコンチキ、チャンチキとも呼ばれたりします。
皿のような形状をしていて、撞木(しゅもく)と呼ばれる棒で皿の内側を叩いて音を出します。
手で持って使ったり、紐で吊り下げて使ったりします。
芝居の下座音楽や郷土芸能、祭囃子、阿波踊りなどに使用され、管弦楽曲でも使われることがありますね。


摺鉦の特徴と使い方:
【奏法】
・紐で吊るすか枠や柄をつけて撞木で打つ
・片手に直接持って持つ指で音色や余韻を変えながら撞木で打つ
【サイズ】
40号(4寸)から70号(7寸)までのサイズがあり、サイズによって音色がちがってきます
【音色】
摺鉦の大きさによって音色が変わり、小さいサイズは高音域、大きいサイズは低音域の音色になります
摺鉦の演奏は、撞木の持ち方や打ち方、鉦を持つ手の指の動きなどで音色が変わってきます。
祭りやお祝い事などのイベントでも頻繁に使用され、その響きは会場全体を盛り上げる役割をしてくれます。
和太鼓の演奏においては、進行の合図やクライマックスの演出などにも使われていますね。
摺鉦は、和太鼓との相性がとても良く、その響きは和太鼓の迫力を一層引き立ててくれます。
和太鼓の演奏には欠かせない和楽器の一つであることは、まちがいなさそうですね。
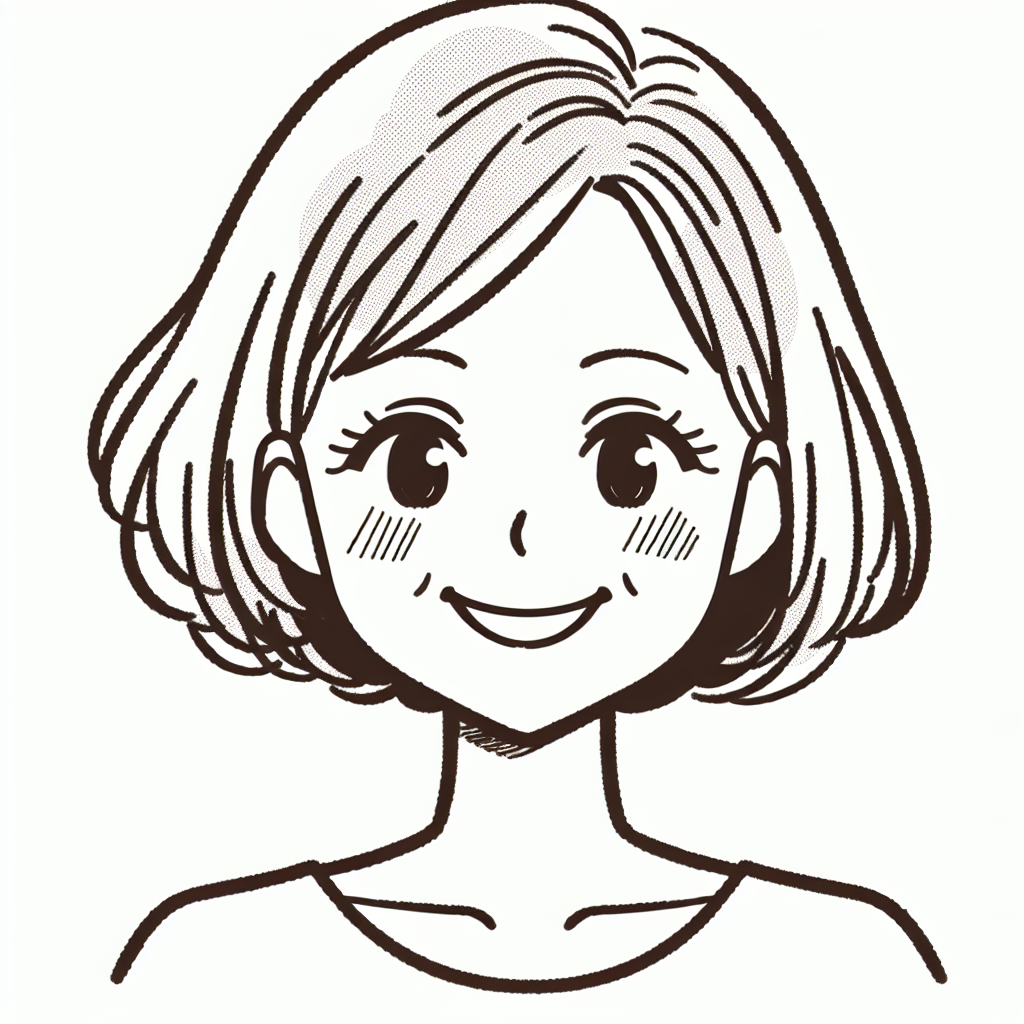
摺鉦の出すリズムが和太鼓演奏のリズムやスピードを左右するときが多々あります。
我がチームは、ひとつの曲に摺鉦担当は一人です。
担当するときは、ちょっとドキドキします。
和楽器・チャッパの紹介
チャッパは日本の伝統的な打楽器の一つで、お祭りの囃子や和太鼓演奏、神楽、歌舞伎などで広く使用されています。

チャッパの特徴
チャッパは2枚の金属製の板が付いた楽器で、手で打ち鳴らして音を出します。
金属の板の形状はシンバルのようになっており、打撃音が特徴的です。
材質は真鍮やブロンズなどの金属が一般的です。
チャッパは和太鼓演奏に華を添える重要な楽器といえます。
チャッパの演奏方法
チャッパは小さなシンバルが二つで一組になった和楽器です。
- チャッパは2枚1組で、両手に1枚ずつ持ちます。
- 手首を回しながら、2枚のチャッパを上下に打ち合わせるように演奏します。
- 打つ強さや速さを変えることで、様々な音色を出すことができます。
使い方は多様で、
打ち合わせて音を鳴らすだけでなく、こするようにして音を鳴らしたり、
打った後に微妙な隙間を開けることでドラムのハイハットのような音を出すようなこともできます。
様々なリズムパターンを作り出すことができ、和太鼓などの演奏に合わせて使われます。
チャッパの音を和太鼓のリズムに合わせるためには、練習が必要となりますが、
和太鼓のリズムを聴きながら、チャッパを叩くタイミングを合わせてみましょう。
うまくタイミングがあってくると、楽しくなって気持ちも盛り上がりってきます。
さらに自信がついてくると、力強い音も出せるようになっていきます。
和太鼓の舞台演奏のときに、チャッパの演者がステージ上を縦横無尽に動き回り、身軽さを活かし、楽しそうに踊りながらリズムをとってパフォーマンスする姿もよく見かけます。
和太鼓演奏には欠かせない楽器といえますね。
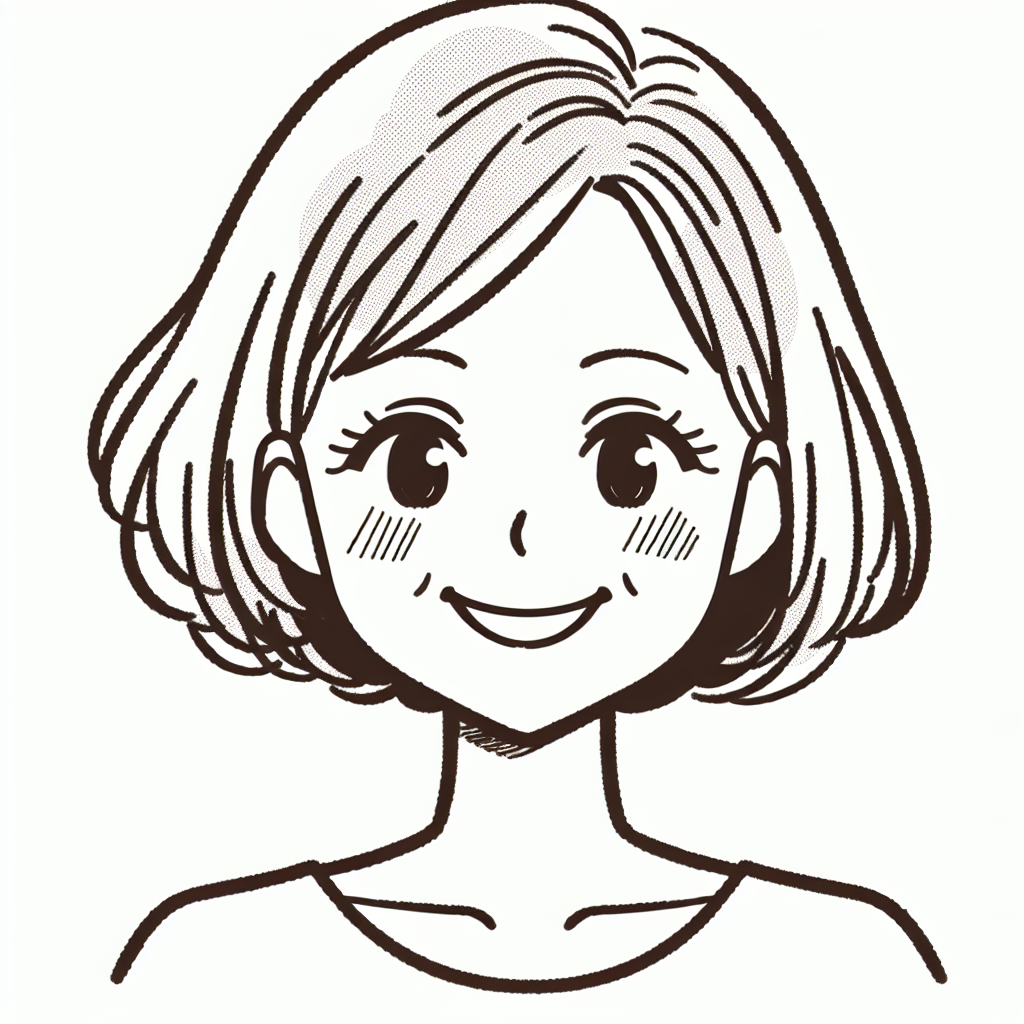
実は、私はまだチャッパを担当したことがありません。
我がチームでは大学生や20代の方がチャッパを演奏し、
ステージを盛り上げてくれています。
すごく、カッコイイです。
まとめ
今回は、和太鼓を彩る和楽器として『篠笛』『摺鉦』『チャッパ』を紹介しました。
和楽器の演奏は、日本の祭りや伝統芸能を彩る重要な要素となっていて、
どれも魅力的な楽器でしたね。
和太鼓を始められたら、この三種の和楽器にもぜひ挑戦してみてください。
和太鼓の世界がぐんと広がり、どんどん楽しくなっていくと思います。



コメント